「金属部門」対策
金属部門は、金属材料・生産システム、表面技術、金属加工の3選択科目があります。すべての科目に対応してご支援いたします。
Pickup!2026年度の技術士試験はこう変わる!−事例をあげて2026年度問題を予想−
(東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・新潟・金沢・広島・高松・沖縄)
【開催日】東京:2026/1/18(日) 大阪:2026/1/31(土) 名古屋:2025/12/21(日)
福岡:2026/1/11(日) 仙台:2026/1/24(土) 新潟:2026/2/28(土)
金沢:2026/2/7(土) 広島:2026/1/10(土) 高松:2026/2/21(土)
沖縄:2026/2/14(土)
[2026年度(令和8年度)試験対策]
予想が外れた時どう対応して合格するか教えます!!
−今からやっておく技術士第二次試験(20部門)対策−
【開催日】東京:2026/3/14(土)
Pickup!技術士試験に合格する正しい生成AI活用法(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/2/23(月・祝) オンライン:2026/2/28(土)
Pickup!技術士第二次試験で問われる気象災害の防災と気候変動適応策
【開催日】オンライン:2026/2/15(日)
Pickup!プロセスチェックの見える化で文章力が大幅に上達する技術士第二次試験合格小論文作成法
【開催日】東京:2026/2/11(水・祝)
Pickup!技術士第二次試験必須科目で問われるコンピテンシーと技術者倫理に合格解答する対応法
【開催日】オンライン:2026/2/8(日)
Pickup!技術士第二次試験必須・選択科目で問われる「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の合格答案論述法(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/1/31(土) オンライン:2026/2/15(日)
Pickup!技術士第二次試験の頻出テーマ「カーボンニュートラル・脱炭素社会」の合格論文作成法(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/1/31(土) オンライン:2026/2/7(土)
Pickup!技術士筆記試験に合格する文章表現力基礎講座「7つの論述テクニック」
(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/1/24(土) オンライン:2026/2/1(日)
Pickup!元試験委員がそっと教える技術士第二次試験合格の秘訣(東京・大阪)
【開催日】東京:2026/1/17(土) 大阪:2026/2/1(日)
Pickup!技術士第二次試験に合格するための修習ガイドブック改訂3.1版活用法(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/1/12(月・祝) オンライン:2026/1/18(日)
Pickup!実践!技術士第二次試験に合格するキーワード集・論文作成講座
(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/1/10(土) オンライン:2026/1/17(土)
技術士第二次試験のための日本語作法(東京・オンライン)
【開催日】東京:2025/12/20(土) オンライン:2025/12/21(日)
2026年度(令和8年度)技術士第二次試験合格のポイント
−受験対策のポイントと対策講座ガイダンス−(東京・大阪・名古屋)
【開催日】東京:2026/1/25(日) 大阪:2026/1/17(土) 名古屋:2025/12/20(土)
[2025年度(令和7年度)口頭試験対策]
令和7年度技術士第二次試験口頭試験 完全合格直前対策講座−マンツーマン個別指導講座
【開催日】ご相談ください
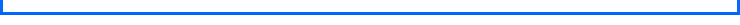
New!技術士第二次試験合格のための「科学技術・イノベーション白書」の読み方(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/3/14(土) オンライン:2026/3/29(日)
New!技術士試験に合格するための「ものづくり白書」の読み方(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/3/8(日) オンライン:2026/3/20(金・祝)
New!技術士試験合格のための「情報通信白書」の読み方(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/3/8(日) オンライン:2026/3/20(金・祝)
New!技術士試験に合格するための「環境白書」の読み方(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/3/7(土) オンライン:2026/3/15(日)
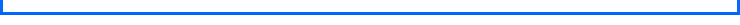
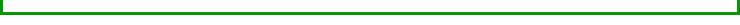
 予想模擬問題が的中!
予想模擬問題が的中!
技術士対策講座の添削用模擬問題や、「直前公開模擬試験」での模擬問題と、ほぼ同内容の試験問題が出題されました。以下にその一例として、過去の試験問題を模擬問題と比較して掲載いたします。当センターの模擬問題は、例年連続して試験問題と類似のものを出題しており、多くの受講者から「問題が的中しました!」と感謝の声をいただいております。
ぜひ皆様も、当センターの指導を受けてください!!
【必須科目 I】
◆令和7年度金属部門 必須科目試験問題
これまで新規の材料の開発には莫大な期間やコストが必要であったが、近年では様々な企業において材料開発における迅速化や、材料製造プロセスにおける最適化を目的にマテリアルズ・インフォマティクスやプロセス・インフォマティクスの導入が積極的に進められている。
(1)金属材料の開発や生産においてマテリアルズ・インフォマティクスやプロセス・インフォマティクスを活用する際、技術者の立場で多面的な観点から3つの技術的な課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
(2)前問(1)で抽出した技術的な課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策について専門技術用語を交えて述べよ。
(3)前問(2)で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)前問(1)〜(3)の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から題意に即して述べよ。
【直前模擬試験問題】
マテリアルズ・インフォマティクス(MI)は、AIやビッグデータ解析を活用した材料開発の革新手法として注目されている。我が国でも2021年に決定された「マテリアル革新力強化戦略」などを通じて支援を強化し、産学官が連携して取り組んでいる。特に、製造業の競争力向上やカーボンニュートラル推進のため、新材料の高速開発が求められている。企業や研究機関では、量子計算やシミュレーション技術を活用したMIプラットフォームの構築が進んでおり、国際競争力強化を目指している。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。
(1)MIの効果的な推進の実現に向けて、金属分野の技術者の立場で、多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、金属部門の専門技術用語を交えて示せ。
(3)前問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)前問(1)〜(3)の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から、題意に即して述べよ。
【選択科目 II】
◆令和6年度金属部門「金属材料・生産システム」試験問題
構造材料の軽量化に向けて、鉄鋼材料の代替として軽量金属であるアルミニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金の活用が考えられている。これら3つの軽量金属のうち1つについて、構造材料として使用する際の特徴的な性質について、鉄鋼材料と比較しつつ述べよ。
【直前模擬試験問題】
アルミニウム合金の種類を複数挙げ、それぞれの特徴、用途および課題について述べよ。
◆令和6年度金属部門「表面技術」試験問題
ステンレス鋼の腐食形態を2つ挙げ、それぞれの特徴を述べよ。
【通信教育添削問題】
ステンレス鋼で発生する腐食についての特徴を説明し、さらに、二相ステンレス鋼の腐食に関わる実用上の注意点を述べよ。
◆令和6年度金属部門「表面技術」試験問題
高速道路におけるトンネル内の定期点検で付帯構造物のケーブルラックに大きな腐食損傷が認められ、その補修を実施することとなった。この業務の担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。
(1)補修に向けての調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
(2)業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。
【通信教育添削問題】
あなたが取り扱っている商品で腐食に関係する不良が頻発する問題が発生した。あなたがこの不良の原因・対策プロジェクトの担当責任者として対策業務を進めるに当たり、この不良問題を具体的に示し、下記の内容について記述せよ。
(1)対象となるプロセスと不良の具体的な内容を挙げ、調査、検討すべき事項とその内容について述べよ。
(2)業務を進める手順を列挙して、留意すべき点、工夫を要する点について述べよ。
(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方法について述べよ。
◆令和6年度金属部門「金属加工」試験問題
金属の粉末を用いる金属射出成形法(MIM)についてプロセスを中心に述ベ、金属の鋳造法との違いについて述べよ
【通信教育添削問題】
金属粉末射出成形(MIM)の製造プロセスを説明し、その特徴を述べよ。
【選択科目 III】
◆令和7年度金属部門「金属材料・生産システム」試験問題
2050年において二酸化炭素の実質的な排出量をゼロにすることを目標としたCN(カーボンニュートラル) 戦略が産業全体で進められている。代表的な金属である鉄鋼の製造においてもCN実現を可能にする生産技術開発が行われている。
(1)二酸化炭素排出の削減に向けて開発・検討をされている鉄鋼製造プロセスに関する技術を3つ挙げて、それぞれの技術課題について述べよ。
(2)前問(1)で抽出した技術課題のうち、最も重要と考えられる課題を1つ選び、その対策を複数述べよ。
(3)前問(2)で示した対策を実行しても、鉄鋼産業だけでは解決されないリスクについて、その対応策を鉄鋼以外の産業との連携の可能性なども含めて展望を示せ。
【通信教育添削問題】
近年、気象変動が自然や人間社会に与える影響が大きな問題となっている。また、温室効果ガスの継続的な排出は、人々や生態系にも深刻な影響を与えていると言われている。そこで、我が国は2050年カーボンニュートラルの目標を掲げ、金属材料の分野でも脱炭素・低炭素に向けて取り組んでいる。
(1)低炭素化社会の実現に向けて金属材料開発を進めるうえでの課題を、金属材料の技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
(3)前問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

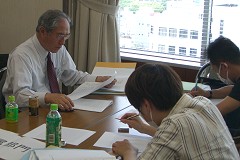
口頭試験も無事合格しました。
U先生へもお礼をお伝え頂けたら幸甚です。
諸事情により、御社の口頭試験対策には参加できませんでしたが、昨年度、購入した口頭事例集は参考になりました。
大変ありがとうございました。
(N様)
スクーリングで解いた予想問題が本番で的中しました。
(N様)
論文の書き方から,学習のスケジュールまで指導いただき大変助かりました。
モチベーションの維持が出来て良かった。
特に他の受講生との交流が非常に効果的だった。
技術士の方と実際に技術的な話をすることが出来,勉強になった。
(S様)
添削が非常に役立ちました。
金属部門の先生の指導に従い、質問通りの章立てを参考にしました。
選択IIIでは、図を入れた方がいいということで直前に、自分なりに答案用の図を用意しました。これらは本試験で実行できたので良かったです。
金属部門も非常に範囲が広く、自分の選択する表面技術の細かい内容までは自分で勉強しなければならならず苦労しました。
しかし、先生からは、選択IIIのヒントになる時事的な内容の講義を受けることができました。しかも、その内容が他の選択科目で出題されていました。
(N様)


太田 芳雄 先生
技術士試験合格のためには、試験に対する若干のノウハウ及び培った専門的知識が必要です。同時に試験準備のためにモチベーションの維持は欠かせません。 資格の取得はあくまでスタートで、登録後のネットワーク形成、他分野の専門家との交流によって技術者としてスキルアップし、幅広く活動することが最終目標と考えます。取得に向けてチャレンジする方々を大いにサポート致します。
ほかの金属部門講師からも、技術士を目指す方へのメッセージをいただきました。
「技術士試験と仕事とは密接な関係がある。技術士に挑戦することにより、専門知識を体系化でき、仕事に生かすことができる。また、日頃の技術的業務に全力投球することが、最大の受験勉強となる。技術士講座を最大限に活用して目標を達成し、新たな将来を築いていこう!。」



A4判・約100頁
定価:4,000円(税込)+送料
定価:4,000円(税込)+送料
A4判・約145頁
定価:4,000円(税込)+送料
A4判・約200頁
定価:4,000円(税込)+送料

A4判・約85頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約110頁
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約85頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約85頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約85頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約80頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約85頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約70頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約70頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約110頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約120頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約70頁
定価:5,000円(税込)+送料


A4判・約80頁
定価:3,000円(税込)+送料
たくさんの金属部門の技術士の方が、当社のセミナー、出版物の著者として活躍されております。
是非、皆様からの企画のご提案をお待ちしております。
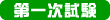
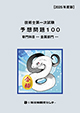



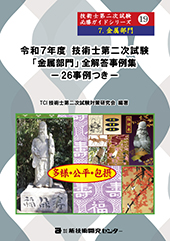






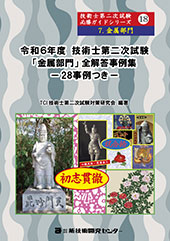
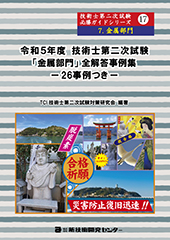
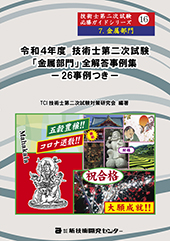
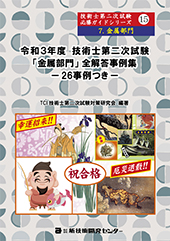
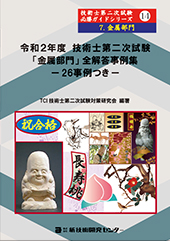
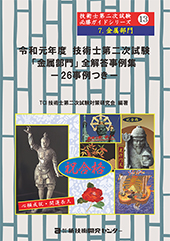
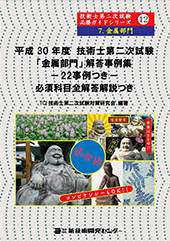
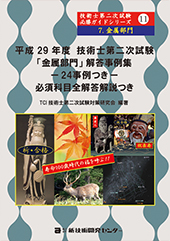
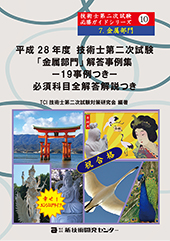
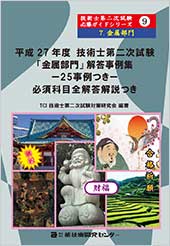
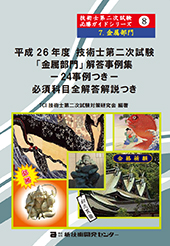
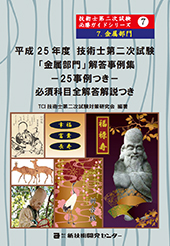





















![[改訂新版]技術士第二次試験新試験のための新しい合格論文の構成と表現法](image_book/book_3162.jpg)


