「機械部門」対策
機械部門は、機械設計、材料強度・信頼性、機構ダイナミクス・制御、熱・動力エネルギー機器、流体機器、加工・生産システム・産業機械の6選択科目があります。すべての科目に対応してご支援いたします。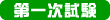
New!2026年度技術士第一次試験実力診断模擬試験(東京・在宅)
【開催日】東京:2026/7/4(土) 在宅:2026年7月上旬送付予定
New!2026年度技術士第二次試験筆記試験直前模擬試験(東京・大阪・名古屋・在宅)
【開催日】2026/5/30(土) 大阪:2026/6/6(土) 名古屋:2026/6/13(土)
在宅:2026年5月下旬送付予定
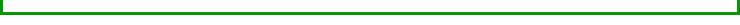
Pickup!2026年度の技術士試験はこう変わる!-事例をあげて2026年度問題を予想-
(東京・新潟)
【開催日】東京:2026/3/15(日) 新潟:2026/2/28(土)
技術士第二次試験に合格するための修習ガイドブック改訂3.1版活用法
(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/5/17(日) オンライン:2026/6/13(土)
New!令和8年度技術士第二次試験「改訂版コンピテンシー」対応
「リスク」と「技術者倫理・持続可能性」完全攻略講座(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/4/18(土) オンライン:2026/4/26(日)
Pickup!コンピテンシー改訂・補足で令和8年度技術士第二次試験はどう変わるか!
【開催日】オンライン:2026/3/29(日)
Pickup!技術士第二次試験合格のためのキーワード集の作り方と論文作成(エッセンス)
【開催日】オンライン:2026/3/22(日)
Pickup!速習指導!!技術士第二次試験II-2の合格答案の書き方(東京・大阪)
【開催日】東京:2026/3/20(金・祝) 大阪:2026/3/8(日)
Pickup!予想が外れた時どう対応して合格するか教えます!!
-今からやっておく技術士第二次試験(20部門)対策-
【開催日】東京:2026/3/14(土)
技術士試験に合格する正しい生成AI活用法
【開催日】オンライン:2026/2/28(土)
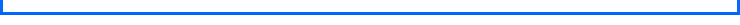
Pickup!技術士第二次試験合格のための「科学技術・イノベーション白書」の読み方(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/3/14(土) オンライン:2026/3/29(日)
Pickup!技術士試験に合格するための「ものづくり白書」の読み方(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/3/8(日) オンライン:2026/3/20(金・祝)
Pickup!技術士試験合格のための「情報通信白書」の読み方(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/3/8(日) オンライン:2026/3/20(金・祝)
Pickup!技術士試験に合格するための「環境白書」の読み方(東京・オンライン)
【開催日】東京:2026/3/7(土) オンライン:2026/3/15(日)
あらゆる白書の上位文書内閣府SIP文書を技術士第二次試験対策に活用しよう!!
【開催日】オンライン:2026/2/28(土)
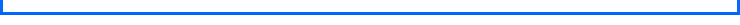
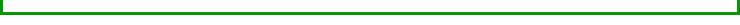
 予想模擬問題が的中!
予想模擬問題が的中!
技術士対策講座の添削用模擬問題や、「直前公開模擬試験」での模擬問題と、ほぼ同内容の試験問題が出題されました。以下にその一例として、過去の試験問題を、模擬問題と比較して掲載いたします。当センターの模擬問題は、例年連続して試験問題と類似のものを出題しており、多くの受講者から「問題が的中しました!」と感謝の声をいただいております。
ぜひ皆様も、当センターの指導を受けてください!!
【選択科目 II】
◆令和7年度機械部門「機械設計」試験問題
近年、積層造形法(3Dプリンタ)を利用した機械部品等の生産が実用化されつつある。積層造形法と従来の生産方法(鋳造、鍛造、研削、溶接、射出成形等)を比較し、積層造形法の利点を述べよ。また、積層造形法で機械部品等を設計する際の留意点について述べよ。
【通信教育添削問題】
具体的な製品に使用する部品を挙げ、3Dプリンター製作品を実用化する場合、材料面、強度面で検討すべき点を3つ述べよ。また、材料面、強度面を考慮した結果、新たに生じる損傷リスクを説明せよ。
◆令和6年度機械部門「材料強度・信頼性」試験問題
高経年の機械設備において、重要部品に亀裂が生じて疲労損傷するという大規模な事故が発生した。当該設備のメンテナンス責任者として、原因究明と今後の対策を講じなければならない。次の設問に答えよ。
(1)亀裂の発生や進展を評価し、原因究明及び今後の対策に繋げるために調査・検討すべき事項を3つ示し、それらの内容について説明せよ。
(2)想定される原因を2つ挙げ、それぞれに対し緊急に取るべき対策とその際に留意すべき点、工夫すべき点を述べよ。
(3)上記の業務のそれぞれを効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。
【通信教育添削問題】
長期間運用してきた機械設備において、劣化した部品の破損やその劣化に伴う周辺部品の破損による動作不良の発生頻度が増加し、その信頼性の低下がみられるようになってきた。そこで当該設備について信頼性回復のための改修を計画的に行うことになった。あなたが当該改修作業の責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。
(1)当該作業に向けて、設備の材料強度・信頼性の観点から調査、検討すべき事項と内容を説明せよ。
(2)業務を進める手順を列挙し、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方法について述べよ。
【選択科目 III】
◆令和7年度機械部門「流体機器」試験問題
我が国において2024年10月に、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」いわゆる水素社会推進法が施行された。
水素社会では、水素の製造や輸送、使用の各場面で流体機器の果たす役割はますます大きなものとなる。このような状況を踏まえて、流体機器分野の専門技術者としての立場で、以下の問いに答えよ。
(1)対象となる流体機器を1つ挙げ、その流体機器が水素の製造や輸送、使用などにおいて用いられる際の技術課題を、技術者としての多面的な観点から3つ抽出し、その内容を観点とともに示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、重要と考えた理由を述べ、その課題の解決策を複数示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行したうえで生じる懸念事項に対する専門技術を踏まえた対応策と、生じる波及効果を示せ。
【通信教育添削問題】
経済産業省は、「2024年度エネルギー白書」において、エネルギーを巡る状況と主な対策の中で、1) 福島復興の進捗、2) カーボンニュートラルと両立したエネルギーセキュリティの確保、3) GX・カーボンニュートラルの実現に向けた課題と対応、を取り上げている。その中で、流体機器の分野で貢献が可能と考えるものとして、1) 次世代洋上風力発電、2) 水素・燃料アンモニア産業、3) CO2回収・活用・貯留、が挙げられる。
流体機器の技術者として、前述の3分野の中の1つに対し、貢献できる流体機器を選定し、以下の問いに答えよ。
(1)流体機器の技術者として貢献できる分野を選定し、対象の流体機器を取り挙げ、多面的な課題を3つ抽出し、その内容を観点とともに示せ。
(2)抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、重要と考える理由を述べ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
(3)すべての解決策を実行したうえで生じる懸念事項に対する専門技術を踏まえた対応策と、生じる波及効果を示せ。

無事合格することができ、努力が報われたことに安堵しております。
ひとえに御社の精度の高い資料と的確な指導によるものと思います。
特に、K先生には断念した昨年度から、大変お世話になりました。
筆記試験、口頭試験共に私の至らない点を的確にご指摘いただかなければ今の結果は得られていなかったと思います。
今後のことはまだ明確には決まっておりませんが、総監部門を受験するなど、機会がありましたら改めてご指導を賜りたく存じます。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
(Y様)
先ほど合格発表を確認しました。
口頭試験の9分延長の時は正直厳しいと思いましたが、御社のご助言のお陰で合格を信じてこの日を待つことができました。助かりました。
O先生にも宜しくお伝えください。改めてありがとうございました。
(O様)
この度、御社の「技術士オンライン講義配信プレミアム講座」と「口頭試験 完全合格直前対策講座」を受講し、無事合格できました。
2つの講座が試験対策にとても役に立ち、感謝しております。ありがとうございました。
添削や口頭試験指導でご尽力いただいた先生方にも、よろしくお伝えください。
(O様)
対策講座において、多大にお世話になりました。結果、無事に合格確認できました。
新技術開発センターのご指導、特に二次試験対策の筆記、口頭対策でご指導を頂いたY様には大変お世話になりました。
また、機会があれば御社講座を利用したいと考えています。ありがとうございました。
(H様)
貴社、講座のおかげで、この度、機械部門にて合格することができました。
受験申込書作成の段階から、ポイントを絞り込んだ対策ができたことが大きかったと感謝しております。
弊社では、技術士の育成を進めており、貴社、講座には引続きお世話になるかと思いますので宜しくお願い致します。
(H様)


赤城 協 先生
『技術士試験の合格率が低いことに、皆さんはハードルの高さを感じていませんか?しかし恐れることはありません。勉強法、解答の作成法、口頭試験の対応法などには、それぞれ押さえるべきポイントがあります。しかも最短で合格を目指すための方法もあります。思い立ったが吉日です。今日から合格目指して頑張りましょう。』
「難関の技術士試験」に合格するコツは、(1)貴方自身が先ず“受験”を決意すること。(2)当センターから、合格実績に裏付けされた質の良い受験情報を得ること、(3)当センター発行の洗練された受験対策図書を確保し、試験本番に向け早期に演習を完了させること。(4)効率の良い演習(学習)の進め方は、指導経験豊富な講師のノウハウを活用し、自分のものにすること。(5)口頭試験準備として、講師の直接指導を必ず受けること。(模擬口頭試験を体験すること)そして(6)自身の合格後の“活躍する姿”を想像して1日1回は心の中で“合格する”と宣言すること。例えば10日間で10回言うことを継続すれば合格が“叶う”と思います。「叶う」は口と十を書きます。貴方の合格が叶うように、講師として誠意をもって全力で貴方を「合格」に導きます。



A4判・約95頁
定価:4,000円(税込)+送料
定価:4,000円(税込)+送料
A4判・約180頁
定価:4,000円(税込)+送料
A4判・約205頁
定価:4,000円(税込)+送料

A4判・約160頁
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約90頁
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約160頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約160頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約165頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約160頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約165頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約160頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約155頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約160頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約150頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約165頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約150頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約150頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約150頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約190頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約150頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約160頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約200頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約60頁
定価:5,000円(税込)+送料
A4判・約155頁
定価:5,000円(税込)+送料


A4判・約80頁
定価:3,000円(税込)+送料
たくさんの機械部門の技術士の方が、当社のセミナー、出版物の著者として活躍されております。
是非、皆様からの企画のご提案をお待ちしております。
2026年度労働安全コンサルタント試験完全合格対策講座(中井知章)
「設計の手戻り予防」60事例による具体的取組み法(伊豫部将三)
4時間でわかる!知識ゼロから学ぶプラスチック技術の基礎(田口宏之)
設計審査(DR=DesignReview)50事例による具体的取組み法(伊豫部将三)
令和8年度労働安全コンサルタント試験合格のポイント(竹内春樹)
















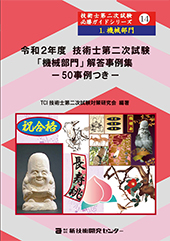





























![[改訂新版]技術士第二次試験新試験のための新しい合格論文の構成と表現法](image_book/book_3162.jpg)


